味覚障害の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |
大阪 鍼灸院(心斎橋) 一鍼堂 >体験談と症例集>味覚障害の東洋医学解説
味覚障害の東洋医学解説
物を食べたわけでもないのに口の中に味を感じる時がある。
糖尿病・歯槽膿漏・蓄膿症・咳・胃腸疾患・肝臓疾患などに
罹患している人は口内に独特の味覚があり、口臭があったり
あるいは、味を感じないことがあったりする。
もちろん、病気に伴う味覚障害は本来の疾患を治療しなければならない。
しかし、病気を持っていなくても味覚異常を感じる場合がある。
東洋医学では口内に感じる味・感じない味は病の兆候を示すものとして
弁証に際して重視される。
味覚障害を主症状として弁証論治をまとめる。
東洋医学的な見解
1. 口苦(こうく)

口苦とは、口中に苦味を自覚することである。
・邪侵少陽(じゃしんしょうよう)
『傷寒論(しょうかんろん)』
少陽病脈証并治 二百六十三章
"少陽之為病、口苦咽干目眩也。"
訳:
およそ少陽病に罹ると、口が苦い、
咽喉の乾燥感、めまいなどの症状が出現する。
傷寒太陽病(しょうかんたいようびょう)が解さずに邪が少陽に伝入し、
胆は「少陽の腑」であることから
胆熱が上蒸(じょうじょう:熱で蒸され上昇する様子)して発生する。
特徴は、口が苦いと同時に
寒熱往来(かんねつおうらい・悪寒と発熱を繰り返す)
・食欲不振・悪心(おしん:吐き気を催すこと)
・胸脇部が張って苦しいなどの
半表半裏証(はんぴょうはんりしょう)である。
治法:
和解少陽(わかいしょうよう:病邪が半表半裏にある病証を治療する方法)
・肝胆鬱熱(かんたんうつねつ)
『黄帝内経・素問(こうていだいけい・そもん)』奇病論篇(きびょうろんへん)
”有病口苦、…病名曰膽癉。
…此人者、数謀慮不快、故胆虚、気上溢而口為之苦”
訳:
病ありて口苦きは、…病名は胆癉(たんたん)という。
…これ人は数(しばしば)謀慮して決せず、
ゆえに胆の虚気は上溢して口はこれがために苦し
『雑病源流犀燭(ざつびょうげんりゅうさいしょく)』
口歯唇舌病源流(こうししんぜつびょうげんりゅう)
”肝移熱於膽亦口苦、内経言膽癉是也。
注云:肝主謀、膽主決、或謀不決、
為之急怒、則氣上逆、膽汁上溢故也。”
訳:
肝は胆に熱を移せばまた口苦く、内経にいう胆癉これなり。
注にいう、肝は謀を主り、胆は決を主る。
あるいは謀りて決せず、これがために急怒すれば
すなわち気は上逆し、胆汁は上溢するゆえなり。
肝胆鬱熱の口苦は、
情緒の抑鬱・五志過極
(ごしかきょく:怒・喜・思・憂・恐の五種の精神情緒が過剰になること)などで化火し、肝胆の鬱火が生じて疏泄が失調し、胆気が上溢して発生する。
治法:
清熱疎肝(せいねつそかん:鬱状態の肝の機能を高め熱を冷ますこと)
解鬱(かいうつ:鬱を解消すること)
2. 口甜(こうてん)

口甜とは、口内に甘味を自覚することである。口甘とも言う。
『黄帝内経・素問』奇病論篇
“有病口甘者…此五気之溢也。名曰脾癉”
訳:
病ありて口甘きは、…これを五気の溢するなり。
名付けて脾癉(ひたん)という。
脾癉は病名であり、口甜はその症状の一つであるから同一のものではない。
・脾胃熱蒸(ひいねつじょう)
『黄帝内経・素問(こうていだいけい・そもん)』奇病論篇(きびょうろんへん)
“肥者令人内熱、甘者令人中満、故其気上溢"
訳:
肥は人を内熱せしめ、甘は人をして中満せしめ、
ゆえにその気上溢す
辛辣なもの・脂っこいもの・甘いものを過食して内熱が生じ
口甜を生じさせることが多い。
この他、湿熱の邪が脾胃に停滞し、
穀気(こくき・こっき:飲食物が持っている気(エネルギー)のこと)
と結びつけて上蒸したために発生することもある。
治法:
清熱瀉火(せいねつしゃか:熱の過剰な状態を改善すること)
・脾胃気陰両虚(ひいきいんりょうきょ)
老化・慢性病などの脾胃の気陰が消耗し、
虚熱が生じて脾津がさらに消耗したために口甜が発生する。
治法:
益気健脾(えききけんぴ:気の作用を高め、脾胃の機能を正常にする)
和胃養陰(わいよういん:冷やし潤す力を補充し胃の機能を正常にすること)
3. 口酸(こうさん)

口酸とは、口内に酸味を自覚することで甚だしければ酸臭がする。
『血證論(けっしょうろん)』口舌
"口酸是濕熱、觀炎天羹肉過夜則酸、便知酸是濕熱所化"
訳:
口酸はこれ湿熱なり。
炎天の羹肉は夜を過せばすなわち酸なるを観て、
すなわち酸は湿熱の化するところと知る。
口酸は呑酸(どんさん:呑酸とは胃中の酸っぱい水分が口内に上ってくること)
とは異なる。
口酸は酸味を自覚するだけで酸っぱい水は上がってこない。
・肝熱上衝(かんえつじょうしょう)
肝経の実熱があり、情緒の抑鬱で
肝鬱化火したり熱邪が肝胆に鬱滞すると、
酸は肝の味であり、肝熱が上蒸するために発生する。
治法:
疎肝清熱(そかんせいねつ:鬱状態の肝の機能を高め熱を冷ますこと)
・宿食停滞(しゅくしょくていたい)
病位は脾胃にあり、
食欲不振・腹満などの症状を呈するところがある。
暴飲暴食・脂っこいものや甘いものの過食などで
脾胃の運化が失調して発生する。
治法:
消食導滞(しょうしょくどうたい:食物の停滞によって起こる腹満、食欲不振、ゲップ、吐き気などに対する治療法)
通降胃気(つうこういき:胃の気を通し降ろす治療法)
4. 口鹹(こうかん)

口鹹とは、口内に塩辛い味を自覚することで、
ときには塩辛い唾や涎を排出することもある。
五臓は五味を主り、鹹は腎の味であり、
腎液が上乗することによって口鹹が発生するので
過労・老化・慢性病などによる腎精不足で
真陰・真陽が虚したためである。
・腎陰虚(じんいんきょ)
腎陰虚では虚火が上炎して腎液を濃縮し、口鹹が生じる。
治法:
滋陰降火(じいんこうか:潤い冷ます陰を補充し、上った熱を下げること)
・腎陽虚(じんようきょ)
陽気が不足して腎液の上泛を摂納できず、口鹹が生じる。
治法:
温補腎陽(おんぽじんよう:腎に宿る陽気・温める力を補充すること)
5. 口膩(こうじ)
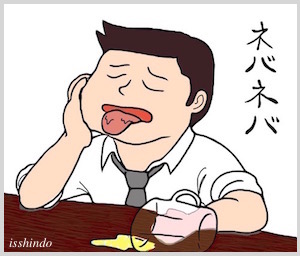
口膩とは、口や舌が粘って気持ちが悪く、
甚だしければ食べても味が分からないことを言う。
・寒湿困脾(かんしつこんひ)
・湿熱中阻(しつねつちゅうそ)
いずれも湿邪による病態であるが、寒熱が異なる。
脾は水湿の運化を主り、津液(しんえき:)を胃に行らす。
湿気のきつい気候・霧露にあたる・水や雨に濡れるなど
湿が侵入したり、生もの・冷たいもの・脂っこいもの・
甘いものなどを過食して脾胃を障害すると
湿邪が停滞して口に上泛し、口や舌が粘って気持ち悪くなる。
寒湿困脾
脾胃虚寒の体質のために湿邪が寒化し、
脾陽を阻害して運化が失調して発生する。
治法:
芳香化濁(ほうこうけだく:湿熱が中焦脾胃や肝胆に蘊醸しているのを芳香化湿の治療方法で治すこと)
健脾燥湿(けんぴそうしつ:湿邪を乾燥させ脾を建てること)
湿熱中阻
脾胃に積熱があって湿熱が上蒸するために発生する。
治法:
清熱化湿(せいねつかしつ:熱を冷まし体内の余分な水分を排出させること)
・痰熱阻滞(たんねつそたい)
脾虚で運化が不足した為に痰湿が生じ
欝して化熱するか、肝鬱化火して津液を濃縮したために
痰が生じ、痰熱が阻滞することにより口膩が発生する。
治法:
清熱化痰(せいねつけたん:熱を冷まし痰を除くこと)
6. 口淡無味(こうたんむみ)

口淡無味とは、味覚の減退で口の中が淡く
飲食物の味のないことを言い、
一般には食べ物の香りもなく食欲不振をともなう。
「口淡」「口不知味」ともいう。
『黄帝内経・霊枢』脈度篇
”脾気通於口、脾和則口能知五穀牟”
訳:
脾気は口に通じ、脾和せばすなわち口はよく穀を知る。
味覚は脾胃との関連が深い。
口淡無味は脾胃の運化失調と関係があり、
病因は気虚による運化の低下と湿邪による運化阻害である。
・脾胃気虚(ひいききょ)
飲食の不摂生・ひどい嘔吐や下痢・慢性病によって、
脾胃の気が虚し運化転輸の機能が低下したために口淡が生じる。
治法:
益気健脾(えききけんぴ:気の作用を高め、脾胃の機能を正常にする)
和胃(わい:胃の機能を回復させること)
・湿困脾胃(しっこんひい)
外邪が脾に侵入したり、暴飲暴食によって
脾の運化が障害されて湿濁が内生し、
湿邪が中焦脾胃を阻害したために口淡が生じる。
治法:
芳香化濁(ほうこうけだく:湿熱が中焦脾胃や肝胆に蘊醸しているのを芳香化湿の治療方法で治すこと)
化湿醒胃(けしつせいい:体内の余分な水分を排出させ、胃を機能させること)
西洋医学的な見解
●味覚障害とは?
味覚はおもに舌で感じます。また軟口蓋、咽頭の一部でも感じます。
味覚障害の症状はさまざまで、部位的には舌の一部や片側が、
また 舌全体が味覚を感じないことがあります。
その程度も濃い味でないと 感じないもの(味覚減退)や、
全く味を感じないもの(味覚脱出)があります。
さらに、本来の味を異なった味に感じる(錯味)こともあります。
薬を飲んだことによっておこる薬剤性味覚障害では、
全体的に味を 感じなくなる、
あるいは一部の味が低下する症状がよく見られます。
原因となる薬には降圧薬、消化性潰瘍治療薬、
抗うつ薬、抗菌薬、抗がん薬などがあります。
亜鉛キレート作用のある薬や唾液分泌をおさえる薬に
味覚障害が起こりやすいと考えられています。
●早期発見と早期対応のポイント
いろいろな薬剤を服用している高齢者では、
発症に至る時間や症 状も様々で、
初期の症状を捉えることは困難なことがあります。
味覚 障害がみられる場合、
薬を服用した後、多くは2~6週間で症状がで ます。
「味を感じにくい」、「食べ物の味が変わった」、「嫌な味がする」
などの症状がみられたら、医師又は薬剤師に相談して下さい。
「口が 乾く、あるいは食事がおいしくない」
などの症状も味覚障害の前ぶれ かも知れません。
薬剤性味覚障害では、発症後できるだけ
早期に原因となる薬物を 中止または変更した方が、
症状の改善が見られることが多いとされています。

1.早期発見と早期対応のポイント
(1)早期に認められる症状 薬剤性味覚障害は高齢者に多く、
複数の薬剤を服用しており、また発症までの時間や症状もまちまちで、
初期の症状を捉えることは困難なことが 多い。
早期症状を含め、よく訴える症状に以下のようなものがある。
①味(甘、塩、酸、苦)が感じにくい
②食事が美味しくない
③食べ物の好みが変わった
④金属味や渋味など、嫌な味がする
⑤味のしないところがある
⑥口が渇く
●副作用の好発時期 原因となりうる薬剤の服用後、
直ぐに発症することもあるが、
多くは約2 週から6 週間以内に味覚障害が起こる。
服用中止後も長期にわたって症 状が継続し、
緩解するまで数か月を要することもある。
●患者側のリスク因子
①性:男女比は 2:3 の割合で、
女性に多いとの報告があるが、その理由は不明である。
②年齢:1980 年代の我が国の報告では、
味覚障害の好発年齢は 50~60 歳代にピークがあったが、
最近では 60 歳以降の発症が多く、
高齢者 に多い疾患であることが認識されつつある。
2003 年の調査によると、 我が国における味覚障害患者は年間 24 万人といわれ、
その数は 1990 年の年間 14 万人から約 1.8 倍に増加している。
その理由の一つと して、急激な高齢化社会を迎えていることが挙げられる。
米国の調査 でも味覚・嗅覚障害患者の約 40%が 65 歳以上であり、
同様の傾向が指摘されている。
③誘因となる疾患:精神神経疾患、循環器疾患、
高血圧症、胃疾患、 肝障害、腎障害、癌などの疾患を
有する患者は薬剤性味覚障害を生じ やすい。
④薬剤の種類の数:薬剤の中には味覚障害を直接、
あるいは間接的に 誘発するものも少なくない。
多数の薬剤を服用している人は、よりリ スクが高いといえる。
⑤薬剤の服用期間:発症リスクは薬剤の服用期間が長期にわたるほど、
服用量が増加するほど高くなる。
●推定原因医薬品(味覚障害を引き起こす可能性の高い薬剤)
薬剤性味覚障害の中で、添付文書に
口腔内苦味感が記されている薬剤を 表 1 に示した 。
その中には催眠鎮静剤、精神神経用剤および循環器官用 薬が多い。
味覚障害・味覚異常が報告されており、
添付文書に記載されている薬剤を表 2 に示した。
味覚障害を起こす薬剤は多品目あり、口腔内 苦味感が記されている
薬剤と同様に循環器官用薬、催眠鎮静剤、精神神経 用剤が多い。
●医療関係者の対応のポイント
味覚障害と薬剤との関連を明らかにする。
薬剤の副作用欄に味覚障害が 明記されている場合や、
主訴や既往歴から原因薬剤の可能性が高い場合は その薬剤の休薬を検討する。
早期に休薬することで症状の改善、回復に至 ることが多い。
原疾患治療のため、休薬が困難な場合は薬剤を変更する。
休薬や薬剤の変更によっても、症状の回復が見られない場合は
口腔外科 や耳鼻咽喉科など味覚検査可能な専門医に紹介する。
●副作用の概要
・自覚症状
味覚障害の症状はその多くが自覚症状である。
その症状は以下のように 分類される。
①味覚減退:「味が薄くなった,味を感じにくい」
②味覚消失・無味症:「全く味がしない」
③解離性味覚障害:「甘みだけがわからない」
④異味症・錯味症:「しょう油が苦く感じる」
⑤悪味症:「何を食べても嫌な味になる」
⑥味覚過敏:「味が濃く感じる」
⑦自発性異常味覚:「口の中に何もないのに苦みや渋みを感じる」
⑧片側性味覚障害:一側のみの味覚障害
薬物性味覚障害では、
①味覚減退、④異味症・錯味症、⑦自発性異常味覚(苦味や渋味)などが多く、
進行すると2味覚消失・無味症に至ること もある。
・他覚症状
薬剤性味覚障害において明確な他覚症状はない。
味覚検査、血液検査などによって、
その症状を把握することはできるが、
患者自身の主観的な 訴えによるところが大きい。
判別が必要な疾患と判別法
味覚障害の原因別頻度については、
薬物性味覚障害が最も多く(21.7%)、 ついで、特発性(15.0%)、
亜鉛欠乏性(14.5%)、心因性(10.7%)、
さらに、嗅覚障害、全身疾患性、口腔疾患、末梢神経障害、
中枢性神経障害 による味覚障害などが報告されている。
以下、判別の必要な疾患について述べる。
①特発性味覚障害:
血清亜鉛値を含め諸検査が正常であり、
原因や誘因 が不明な味覚障害である。
その大部分は食事性潜在性亜鉛欠乏症とさ れ、亜鉛製剤投与が有効な場合が多い。
血清亜鉛値や各種の検査で味 覚障害の原因となるような
異常が見つからない場合に特発性と診断する。
②亜鉛欠乏性味覚障害:
血清亜鉛値の低下が証明され、
かつ、それ以外 に味覚障害の誘因や原因が明確でない症例である。
味蕾には亜鉛が豊 富に含まれており、亜鉛が欠乏すると、
味蕾の味細胞の分化が遅延し、
味覚受容体の感度の低下につながると考えられている。
偏食、不規則 な食習慣、食品添加物
(ポリリン酸、フィチン酸、EDTA 含有)などが 原因となり、
亜鉛の吸収を妨げたり、体内の亜鉛が排泄されることによると考えられている。
診断は一般的には、血清亜鉛値は 69μg/dl 以下を低値とする。
③心因性味覚障害:
軽度のうつ病、仮面うつ病、
転換ヒステリー、神経 症、神経性食欲不振に伴い
味覚障害を発症することがある。
このような患者は心療内科等にコンサルトすることが望ましい。
④風味障害(嗅覚障害):
味覚障害を訴えるが、実際は嗅覚障害である症例がある。
味覚機能に異常のない嗅覚・風味障害と
味覚・嗅覚の両者 の障害が合併することがある。
原因として感冒罹患が最多である。
ウ イルス感染により嗅覚や味覚を司る神経が障害を受けることによる。
感冒罹患後、直ちに味覚障害を自覚した場合にはこの可能性が極めて 高い。
⑤全身性味覚障害:
糖尿病、急性、慢性肝障害、腎不全、甲状腺機能低 下、
胃・腸切除などの患者で味覚障害が生じやすい。
⑥口腔粘膜疾患:
カンジダ感染症、舌炎、舌苔、口腔乾燥により、
味蕾 の萎縮や味物質の味細胞への運搬が障害される。
口腔粘膜疾患の診断 特殊な舌炎として鉄欠乏性貧血、Hunter 舌炎がある。
⑦末梢神経障害:
舌・咽頭部の悪性腫瘍手術、中耳や扁桃の手術、
外傷、 顔面神経麻痺(Bell 麻痺、Ramsay Hunt 症候群など)に伴い生ずる。
⑧中枢神経障害:
脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、頭部外傷、多発性硬化症、
末梢神経障害などにより生ずる。
⑨放射線治療:
放射線照射により味細胞障害、神経障害、唾液分泌障害、 循環不全が起こる。
放射線照射 1~2 か月後がピークで、その後 1~2 年でかなり軽快化する。
上記1、2、5において亜鉛欠乏が直接的、
間接的に関与しており全体 の約 70%におよぶとされる。
●治療方法
治療の基本は、原因薬剤を特定し早期に中止することである。
既に述べ られているが味覚障害を起こすと考えられる薬剤の数は多い。
複数の薬剤 を投与されていることが多く、
特定するのに困難を極めることもある。
また循環器系薬剤などで中止が困難な場合もある。
原疾患の専門医との連携 が大事である。
味覚異常は人の感覚による
判断であるため症状の経緯がわかりにくい。
また急激な改善も期待しにくい。
このことから、治療当初から
改善には時 間がかかることを説明しておく必要がある。
さらに原因となる薬剤を投与される原疾患の重要性から
原因薬剤が中止できない場合もあることを
十分に説明しておかねばならない。
治療の要約
①原因薬剤の中止・減量
②亜鉛剤の補給(味蕾の再生促進を期待して補給)
処方例) ポラプレジンク 1.0g/日 (保険適用外)
処方例) 硫酸亜鉛ZnSO4・7H2O(試薬。亜鉛量23mg)を3回/日、 など
③口腔乾燥の治療・唾液流出の促進、
口腔の湿潤を保ち、唾液分泌 を促進する。
処方例)
人工唾液
処方例)
麦門冬湯 9.0g/日 など 4 口腔清掃とケア、
含嗽、衛生不良な不適合な義歯などの修理または再制作
薬剤性味覚障害の治療法としては、
上記①、②の治療法の重要度が高い。
必要に応じて③、④を行う。
さらに鉄剤、ビタミン剤、漢方薬なども有効 なことがある。
なお、原疾患に注意しながら治療を行う。
出典:厚生労働省H.Pより
[記事:為沢]
参考文献:
『黄帝内経 素問』
『黄帝内経 霊枢』
『中医弁証学』
『[標準]中医内科学』
『いかに弁証論治するか 【続編】』
『中医基礎用語辞典』 東洋学術出版社
『症状による中医診断と治療』 燎原書店
イラスト:為沢画















