結膜炎の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |
大阪 鍼灸院(心斎橋) 一鍼堂 >体験談と症例集>結膜炎の東洋医学解説
結膜炎の東洋医学解説
結膜炎
結膜は、気輪とも呼ばれ、肺の臓との関連が深い。
肺は五行でいえば金に配当されるが
金の色は白がよいとされ、
金に属する気輪の色は白く光沢があるものが正常とされている。
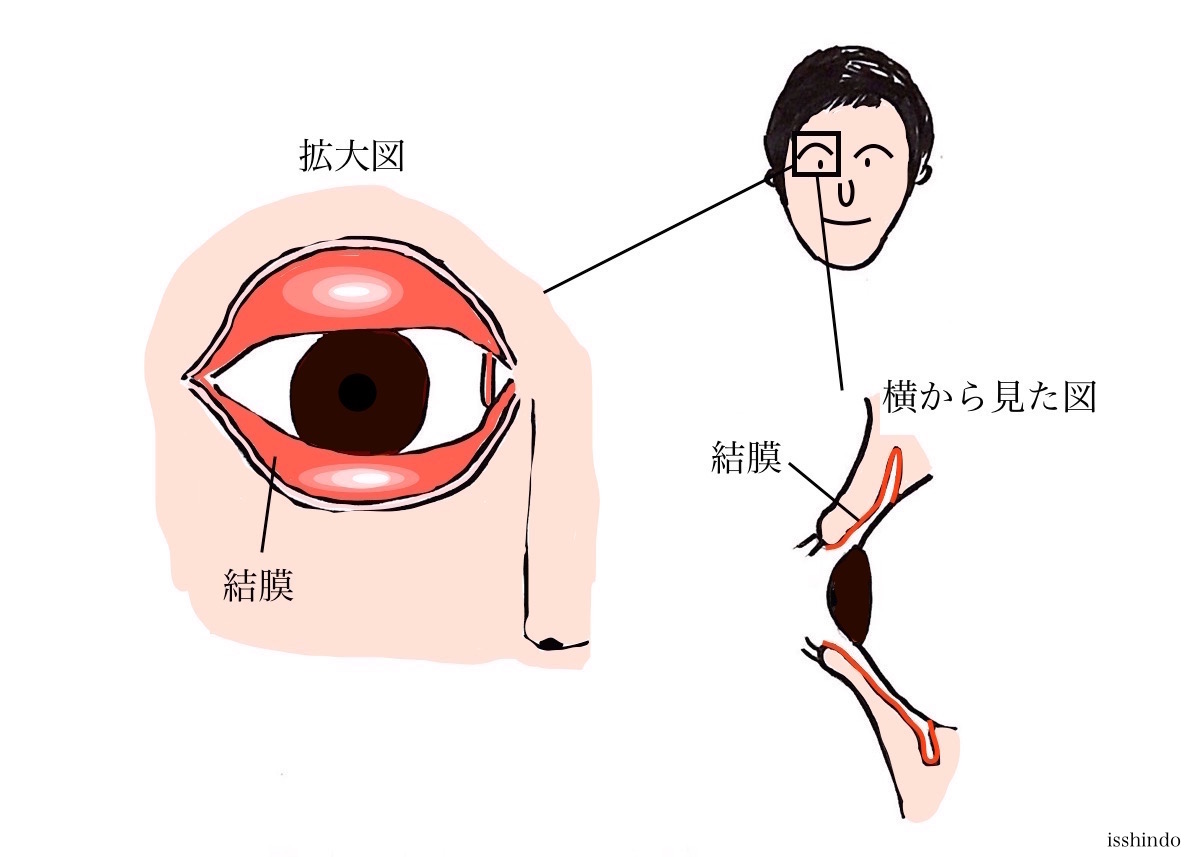
結膜炎の代表的な症状である、
・目の充血
・目の乾燥
・目の痒み
を中心に記載していく。
【目の充血】
目赤(モクセキ)、火眼(カガン)、紅眼(コウガン)ともいわれる。
古典によると
“目不因火則不病,白輪變赤,火乘肺也。”
訳:
目は火によらざればすなわち病まず、
白輪の赤に変ずるは、火は肺に乗ずるなり
《銀海指南(ギンカイシナン)より
著者:顧錫(コセキ)(清時代の人)》
とある。
【目の痒み】
中医学では目痒(モクヨウ)と称し、
軽症では痒みが遊走性であるが、
重症では虫がはうような強い痒みは
痒如虫行(ヨウジョチュウギョウ)と称される。
古典によると
“痒有 因風 因火 因血虚而痒者”
訳:
痒は風により、火により、血虚によるものあり
《審視瑶函(シンシヨウカン)より
著:傳仁宇(デンジンウ/生没年不詳(明時代(1368年~1644年)の人)》
とある。
【目の乾燥】
古典では、
“目之白珠肺也,燥則眵干作癢”
訳:
目の白珠は、肺なり、燥けばすなわち眵(シ:目やに)乾き痒を作す
《銀海指南(ギンカイシナン)より
著者:顧錫(コセキ)(清時代の人)》
また、
審視瑶函(シンシヨウカン)には、
白渋症(ハクジュウショウ)という記載があり
“不腫不赤,爽快不得,沙渋昏朦,
名曰白渋,気分伏隠,脾肺湿熱。”
訳:
腫れず赤ならず、爽快は得ず、
沙渋昏朦(サジュウコンモウ)す、名づけて白渋という。
気分伏隠、脾肺湿熱す。
とある。
両目が乾燥してざらざらした異物感があり、
目の疲れを伴うことをいう。
・目乾渋(モクカンジュウ)
・乾渋昏花(カンジュウコンカ)
ともいわれる。
---------------------------------------------------------------------------------
【中医学的な見解】
風熱(フウネツ)
風熱の邪が肝胆の経脈に入ったり、
それらが経絡をつたって上にのぼり目を犯すことで発生する。
症状:両目の強い痒み、光を見ると眩しい、流涙、充血など
治法:疎風清熱(ソフウセイネツ:風を通し、熱を冷ます)
風寒(フウカン)
風寒の邪が肺肝の経脈に侵入することで発生する。
目に冷風が当たると症状が増悪する。
症状:両目の痒み、流涙、稀薄な目やに、など
治法:祛風散寒(キョフウサンカン:風をはらい、寒を散らす)
燥熱(ソウネツ)
燥熱の邪によって津液が消耗することで発生する。
症状:両目の乾燥・熱感・痒み、口や鼻の乾燥、口渇など
治法:清熱潤燥(セイネツジュンソウ:熱を冷まし、燥を潤す)
実火(ジッカ)
七情(シチジョウ:喜、怒、憂、思、悲、恐、驚という7種類の情志活動)
が乱れることで、肝鬱化火(カンウツカカ:肝経の気が鬱滞して熱と化した状態)し、
火熱が肝胆の経絡にそって目に入り生じる。
症状:両目の充血・痛み、口の苦味、喉の乾燥など
治法:清熱瀉火(セイネツシャカ:熱を冷まし、火を散らす)
血虚(ケッキョ)
肝腎が共に虚すると、
精血(セイケツ・精は血を化生し、
血は精が不足すると精に変化して精を補充する。
これらの関係を「精血同源」とよぶ)が
不足して目を栄養出来ず、
さらに虚火が上炎するために発生する。
症状:目の充血・乾燥・疲れ、異物感など
治法:養血活血(ヨウケツカッケツ:血を養い、血の流れをよくする)
---------------------------------------------------------------------------------
西洋医学における結膜炎
【結膜とは】
結膜は目の表面をおおう薄い透明な粘膜で、
黒目(角膜)かくまくのまわりの白目の表面と、
まぶたの裏をおおうピンクの部分からなっている。
目の表面の粘膜には、目に入ってきた異物や
病原体が目の中に侵入するのを防ぐはたらきがある。
【症状】
結膜炎になると白目が充血して赤くなり、
「めやに」がでたり、涙がでる。まぶたがはれることもある。
黒目(角膜)や茶目(虹彩)の炎症では黒目のまわりから赤くなるが、
結膜炎では、まず目もとや目じりに近い白目が充血する。
その原因には細菌、ウイルス、クラミジアなどの病原体や、
花粉やハウスダストによるアレルギーがあげられる。
【種類】
●ウイルス性結膜炎
細菌よりも小さい微生物であるウイルスに感染することで起こる。
原因ウイルスと症状によって、下記にの種類に分かれる。
・流行性角結膜炎
主にアデノウイルス(8型、19型、37型、54型など)によって起こり、
通称“はやり目”と呼ばれている。
ウイルス性結膜炎のなかでも症状が強く、
充血や目やに、涙、まぶたの腫れ、痛みなどが生じる。
一般的には10日ほどで治まるが、
治りかけのころに黒目(角膜)に点状のにごりが出ることがあり、
瞳にかかってしまうと消えるまで視力が低下することがある。
治療には、副腎皮質ステロイド薬の目薬を使うことがある。
・咽頭結膜熱
アデノウイルス(3型、4型、7型)などによって起こる。
子どもがプールの水を介して感染することが多いことから、
別名“プール熱”とも呼ばれている。
充血や目やになどの他に、喉の痛みや発熱、
下痢など、風邪と似たような症状が現れることも特徴である。
発症後、およそ10日でよくなることが多い。
アデノウイルスを根本的に治療する薬はないため、
のどの痛みには鎮痛薬、高熱には解熱薬など、
それぞれの症状を抑えるような薬が処方される。
・急性出血性結膜炎
エンテロウイルス70型や
コクサッキーウイルスA24型によって起こる。
結膜下出血を起こして目が真っ赤になることと、
強い感染力があることが特徴。
潜伏期間は1日と短く、発症後は1~3週間ほどでよくなっていく。
根本的な治療法はないが、細菌の二次感染を防ぐ目的で、
抗菌薬などが用いられるが、
流水下で手指を石けんで十分に洗うことや、
タオルなどの共有をさけるといったことを
徹底するといった感染予防を行うことが重要とされている。
●細菌性結膜炎
特徴的な症状は、黄色っぽい目やにと白目の充血である。
この症状を引き起こす細菌を「原因菌」というが、
この「原因菌」には多くの種類がある。
具待機的には、インフルエンザ菌、肺炎球菌、
黄色ブドウ球菌、クラミジア菌及び淋菌が挙げられる。
感染の可能性はまれだが、
体力の落ちている人や乳幼児に感染のリスクがある。
治療に関してはウイルス性と違い
有効な目薬(抗生物質)があるので、
きちんと使用すれば短期間で完治する。
●アレルギー性結膜炎
花粉やハウスダストなど、
アレルギーを引き起こす特定の物質により引き起こされる。
アレルギー源は体質によりさまざまで、
特徴的な症状に、まぶたのかゆみと白っぽい目やに、
白目の充血があげられる。
治療には、
抗アレルギー点眼薬(抗ヒスタミン薬、ケミカルメディエータ遊離抑制薬)が、
主に使われる。
重症の場合には、
ステロイド点眼薬や免疫抑制点眼薬などを使用する場合がある。
●クラミジア結膜炎
クラミジア・トラコマティスが原因で起こる病気には、
トラコーマという結膜の炎症を起こす眼病がある。
結膜に炎症を起こすトラコーマは、
悪化すると失明する可能性がある症状の重い病気だが、
その多くは衛生環境が整っていない発展途上国で発症している。
治療には抗生物質を含んだ点眼薬や眼軟膏を使用する。
[記事:新川]
---------------------------------------------------------------------------------
参考文献:
『和訳 審視瑤函 (巻上)』六然社
『中医弁証学』
『黄帝内経 素問』
『黄帝内経 霊枢』
『中医病因病機学』
『[標準]中医内科学』
『中医基本用語辞典』
『やさしい中医学入門』
『いかに弁証論治するか』 東洋学術出版社
『基礎中医学』
『症状による中医診断と治療』 燎原書店















