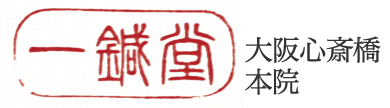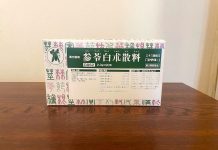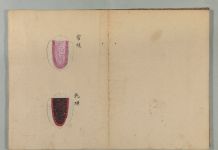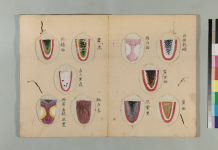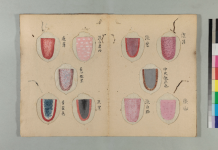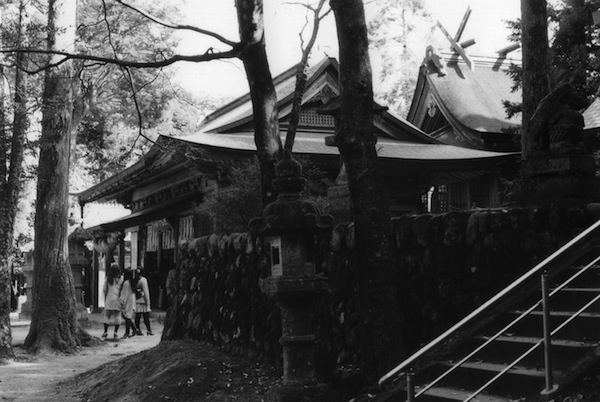前回の記事の続きです。
内容として、素問 四気調神大論篇にはなぜ「土」が出てこない?といった内容でした。
多くの人がこの様な思考回路になる原因ですが、日本では五行の勉強をする時、五行色体表を丸暗記させ、相生・相剋関係について触れるくらいの勉強しかしません。
過去、鍼灸学校・漢方メーカーの勉強会・国際中医師の勉強をしていても皆同じ様な教え方だった印象を受けます。(あくまで個人の経験・感想です)
つまり、この教わり方をすると、五行間のパワーバランスは均等であると言った様な印象を受ける様になります。
中国の中医薬大学の共通教材である「全訳 中医基礎理論 たにぐち書店」を読んでいても全体的には同じ印象を受けました。
現代の中医学では五行を考える際、基本的な認識がこの認識なのだと思います。
しかし、全訳 中医基礎理論には一文だけサラッと
「土は四行(土を除いた五行)を載せる」とあります。
ここに素問 四気調神大論篇の「四時」といったキーワードを結びつけると理解できます。
つまり黄帝内経では土が五行の中でも重要視されている様子が伺えます。
これをヒントに色々調べると黄帝内経には「土王説」という考えが採用されている事がわかりました。
陰陽五行説ーその発生と展開ー じほう 根本光人監修 P 84
「土王説とは五行はすべて同格ではなく、土が他よりも一段強い立場にあるという説で、それゆえ中央に位置し、他の四行に影響を与え続けているという考え方である。」
他の四季についても中央にある土の上で成り立っている様な印象を受けます。
このあたりは史記 五帝本紀や菅子 四時篇を読んでもイメージがつきやすいかと思います。
(よくよく考えると、そもそも「黄」帝内経と言ってるくらいですし…)
最初の中医学の教育の話に立ち返ると、五行に限っては、相生説と相剋説は教えるが、土王説は基本的に教わらない内容となっているとも言えます。
また、季節へのより具体的な土による影響について書かれた本もあるので、ご興味のある方は「東洋医学講座 第一巻基礎編ー宇宙と人体の生成の原理ー 自然社 小林三剛著」を読んでいただくと面白いかと思います。
黄帝内経には他にも自然感について掘り下げていくと面白い内容があります。
そのあたりについても後々書いていきたいと思います。
参考資料:黄帝内経 素問上巻 東洋学術出版社
陰陽五行説ーその発生と展開ー じほう 根本光人監修
全訳 中医基礎理論 たにぐち書店