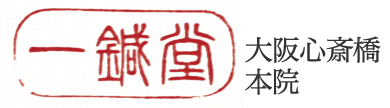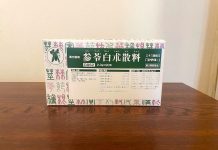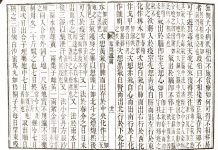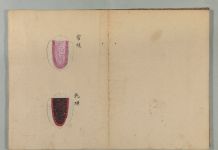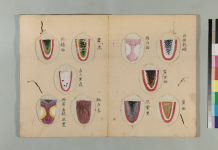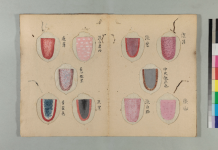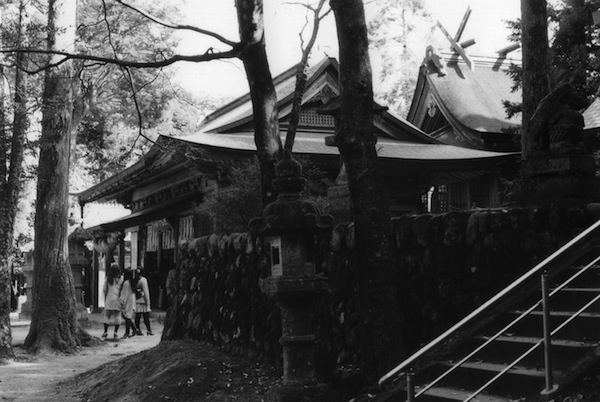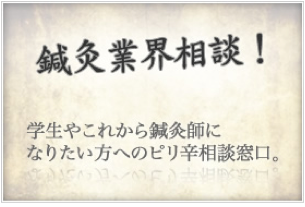こんにちは。
日下です。
先日Xにて素問「四気調神大論篇」について簡単に書きました。
その内容について、自分なりに考えている事を数回に分け、深掘りした内容で書いていきます。
四気調神大論篇は、季節を春夏秋冬の四季に分け、それぞれ3ヶ月に応じた養生法が書かれおり、健康に過ごす方法が書かれた大変重要な篇です。
この篇を読み、季節によって過ごし方が違うと初めて知った時はカルチャーショックを受けました。
昔の人はそこまで意識していたのかと。
しかしよくよく考えてみたらこの内容、納得できないところもあります。
肝心肺腎が出てくるので、五行が絡んでいます。
なのになぜ脾は出てこず、「四季」と四分割され、完結させているのか。
五行色体表の五季で出る「長夏」の養生法がないのは何故なのか。
五行の土の要素が見当たらず、腑に落ちずにしばらくモヤモヤしていました。
しかし、周辺の篇をよくよく読んでみると、
その前の上古天真大論篇に
「聖人なる者あり。天地の和に処り、八風の理に従い…」
「賢人なるものあり、法は天地に則り、象は日月に似り、星辰に弁列し、陰陽に逆従し、四時を分別し、将に上古に従って、道に合同せんとす。」
と書かれてあります。
なるほど!
この辺りの文章に答えがあったのかと気づきました。
次回に続きます。
参考資料 現代語訳 黄帝内経素問 上巻 東洋学術出版社