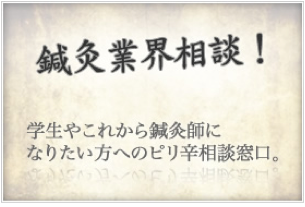どうも、新川です。
年末年始は例年になく、
長いお休みをとらせていただきました。
なんとなく公園にいってみたりと、
意味があるようなないような時間が楽しかったですね。

画像は、
その公園の裏手にひっそりと咲いていた椿です。
———————————————————————————
ここからが本篇です。
『温病条辨』巻首 原病篇
の続きを 綴って参ります。
温病条辯
【巻首 原病篇】
《熱病篇》曰、
「熱病三日、而気口静、人迎躁者、取之諸陽、五十九刺、
以瀉其熱而出其汗、実其陰以補其不足者。
身熱甚、陰陽皆静者、勿刺也。
其可刺者、急取之、不汗出則泄。
所謂勿刺者、有死徴也。
熱病七日八日、動喘而弦者、急刺之、汗且自出、浅刺手大指間。
熱病七日八日、脈微小、病者溲血、口中乾、一日半而死。
脈代者、一日死。
熱病已得汗出、而脈尚躁、喘、且復熱、勿刺膚。喘甚者死。
熱病七日八日、脈不躁、躁不散数、後三日中有汗。
三日不汗、四日死。
未曾汗者、勿腠刺之」
→《熱病篇》に曰う、
「熱病三日にして、気口静かに、人迎躁の者は、これを諸陽に取り、五十九刺し、
以て其熱を瀉して其汗を出だし、其陰を実し以て其不足を補う。
身熱甚だしく、陰陽皆静の者は、刺すこと勿きなり。
其刺す可き者は、急ぎこれを取り、汗出でざるも則ち泄す。
所謂刺すこと勿き者は、死徴有るなり。
熱病七日八日、動喘にして弦の者は、急ぎこれを刺せ、汗且に自ら出でんとす、手の大指間を浅刺す。
熱病七日八日、脈微小、病者溲血し、口中乾くは、一日半にして死し。
脈代の者は、一日に死す。
熱病にて已に汗出づるを得て、脈尚躁、喘し、且つ復ま熱するは、膚を刺す勿かれ。喘甚だしき者は死す。
熱病七日八日、脈躁ならず、躁にて散数ならざるは、後三日中に汗有り。三日に汗せざるは、四日に死す。
未だ曾つて汗せざるは、これを腠刺勿かれ」
———————————————————————————
この条では、
黄帝内経霊枢の《熱病篇》から引用し、
熱病の死候と禁針の症例が述べられている。
概要:
陽熱が盛んでも、陰があまり損傷していなければ、
瀉熱することで、熱が解かれることで陰が自然と補われる。
陰精が消耗していると、湯液で陰を補う。
その場合、鍼は禁忌、または慎重に行う必要がある。
熱病の初期で「気口静、人迎躁」を呈するのは、
邪が軽浅で上焦にあることを示し、
陽経に取穴して陽邪を外泄し、陽気を通じさせて汗を出させるのがよい。
「其陰を実し以て其不足を補う」とは、
陽熱が盛んであると、陰液が消耗し、
陽熱を瀉すことで陰液の消耗を防止することにつながることを示す。
☆葉子雨(清末の人、《評呉瑭氏温病条弁》の著者)によると、
「熱病を治するに補陰を知るは、是最も扼要(要点をえている)の処為り、
陽の有余を瀉すを知るは、即ち陰の不足を補う所以、僅かに増液諸湯を恃むのみならず・・」
陰分を補うことが要点だとしている。
高熱があるのに、脈の陰陽が静であるのは、
陽証に陰脈で、脈と証が合致しない危証なので
刺してはならない。
熱病が7~8日経過し、
呼吸が促迫、躁動する弦脈を呈するものは、
肺熱が激しいものであるので、
少商穴に浅く刺鍼し、肺熱を汗とともに外泄させる。
熱病が7~8日経過し、脈が微細、
熱邪が下焦血分に入り気血を損傷させると、尿中に出血し、
腎精を消耗して陰液が口まで届かなくなると、口渇を呈す。
陰陽ともに衰えると死期が近いが、
脈に少しでも力があれば救える可能性がある。
熱病で汗が出たのに、脈が躁で呼吸困難を呈しているのは、
邪熱が肺陰を消耗させているので、重症度は高い。
熱病が7~8日続き、
脈が躁でないのは邪熱がほとんど解したことを示し、
また躁であっても散大や疾数でないのは、
熱盛ではあるが陰精が消耗していないので、予後はよい。
ただし、汗が出ない場合は陰精が枯渇していることを示し、死期が近い。
続く
参考文献:
『黄帝内経素問』
『黄帝内経霊枢』
『中国医学の歴史』 東洋学術出版社
『中医臨床のための温病条弁解説』医歯薬出版株式会社
新川